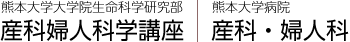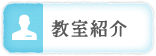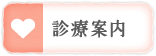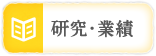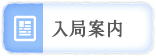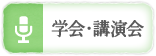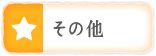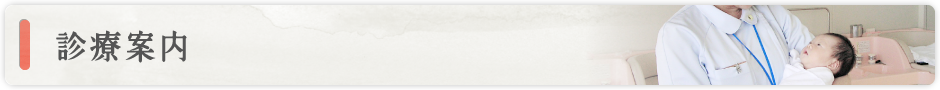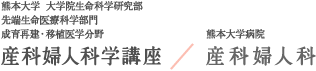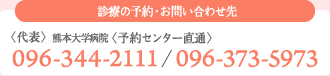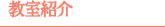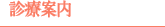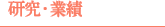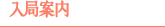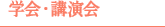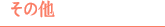診療実績
婦人科
1.スタッフ

診療科長(教授) 近藤 英治(こんどう えいじ)
准教授1名、講師2名、助教4名、診療助手3名、医員11名
2.診療科の特徴、診療内容
婦人科臓器(外陰、腟、子宮頸部、子宮体部、卵巣、卵管、腹膜、胎盤)の腫瘍性疾患、不妊症・内分泌疾患、婦人科領域の感染症、更年期、老年期について、同じく女性を診療する部門である周産期診療と密接に協力しつつ、女性に対する全人的な診療を行っている。
外来は、日本産婦人科学会専門医による診療を基本とし、超音波断層法装置、腟拡大鏡や子宮鏡による検査、CO2レーザー装置を用いた治療を行っている。
入院診療では、中心となる婦人科悪性腫瘍に対して、手術、化学療法、放射線療法、化学放射線療法を駆使し、消化器外科、泌尿器科、放射線治療科や病理部の協力を得て集学的に治療している。
化学療法は入院だけでなく、積極的に外来化学療法センターで行っている。
治療後の生活の質(Quality of life)を重視した治療を行っており、特に骨盤リンパ節郭清術後のリンパ浮腫発生予防のためセルフマッサージを指導し効果を上げている。さらに、若年者においては将来妊娠が可能であるように妊孕性の温存を考慮した治療を行い、妊娠に合併した婦人科疾患に関しては、周産期分野のスタッフと密接に連携して診療に当たっている。
3.診療体制
外来診療体制
新来・再来の診察日は月・水・金で、腫瘍外来、腹腔鏡担当外来、更年期外来、漢方外来、骨粗鬆症外来、排尿調節外来、不妊症(ART)外来、思春期外来、女性医師担当外来の専門外来を設けている。
不妊症(ART)外来は月?金の毎日、思春期外来は火曜日に、子宮頸癌ワクチン外来は水曜日午後に行っている。外来化学療法も行っている。
病棟診療体制
毎週月曜日午後には病棟回診と術前カンファレンスで十分な討論を行い手術に臨んでいる。
予定手術を火曜・木曜日の午前・午後、金曜の午後に行い、緊急手術も含めると週10例程度の手術を行っている。手術は教授以下経験豊富な医師が執刀するが、若手医師への指導も積極的に行っている。
病棟では、指導医が研修医を1対1で指導しており、病棟稼働率約90%、平均在院日数10日未満と、良好な運営を行っている。
4.診療実績
過去12年間(2001年~2012年)の子宮頸がん症例数の推移
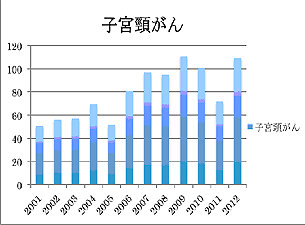
過去12年間(2001年~2012年)の子宮体がん症例数の推移
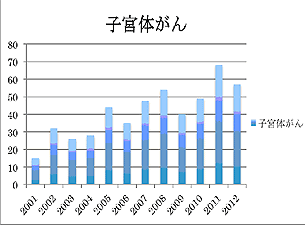
過去12年間(2001~2012年)の悪性卵巣腫瘍症例数の推移
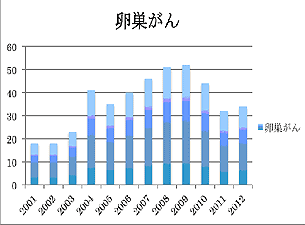
婦人科における悪性腫瘍症例数は200例に及び、九州内の施設でトップクラスである。3大疾患である子宮頸がん、子宮体がん、卵巣がんの各々の症例数はグラフのように増加傾向にあり、10年前のおよそ2倍に達している。
手術の件数等
症例数の増加とともに婦人科手術件数も増加傾向であり、2012年には417件に上っている。
悪性腫瘍に対する開腹手術のほかに、良性疾患に対する内視鏡下手術を積極的に導入しており2012年は腹腔鏡下手術50例を行った
5.高度先進的な医療の取り組み
先進医療に向けた研究
卵巣癌の発生母地である卵巣表層上皮に関する研究は、卵巣癌に対する先進的治療の開発に不可欠である。我々は染色体の安定した不死化ヒト卵巣表層細胞のcell lineを樹立し、この細胞株を用いた卵巣癌発生のメカニズムに関する研究や卵巣癌幹細胞の研究を行っている。
これらの研究からは卵巣がん発生の予防や予知といった先的な治療に結びつくことが予想される。また進行例で発見されることが多い卵巣癌の進展には腹腔マクロファージ、特にM2マクロファージが関与しており、これに由来するサイトカインなどをはじめとする生理活性物質の役割が明らかにすることによって、卵巣癌に対する先進的治療の糸口になると考えられる。
現在、科研費を得て行っている下記の研究については婦人科がん治療に関する先進的医療に向けた基礎的研究である。
6.臨床試験・治験の取り組み
科研費による研究
令和2年度の科研費は下記9件であった。
- ①片渕 秀隆 基盤研究(C)
環境物質の経卵管的な卵巣暴露による発癌機構の解明から導かれる卵巣癌予防の外科戦略 - ②大場 隆 基盤研究(C)
糖尿病の影響を受けた胎児の形態異常に関わる遺伝子のエピゲノム変異に関する研究 - ③田代 浩徳 基盤研究(C)
子宮頸癌前癌病変におけるYAP1活性化と内分泌環境因子との関連について - ④本原 剛志 基盤研究(C)
腫瘍随伴マクロファージの免疫学的動態の制御による卵巣癌に対する新規治療戦略の開発 - ⑤齋藤 文誉 基盤研究(C)
内分泌学的因子を包含した新たな子宮内膜癌の分類と新規治療戦略の確立 - ⑥山口 宗影 若手研究(B)
プロラクチンを介した子宮内膜癌の発癌;増殖機構の解明と新たな予防・治療戦略 - ⑦伊藤 史子 基盤研究(C)
原発性卵巣不全患者における減数分裂関連因子異常の探索 - ⑧坪木 純子 若手研究(B)
上皮性卵巣癌の治療過程におけるM2マクロファージの変化と新規治療戦略への応用 - ⑨竹下 優子 若手研究(B)
卵巣癌におけるANGPTL2標的とした新たな治療戦略の開発
7.地域医療への貢献
セミナーや講演会の開催
毎年2~3月に日本産科婦人科学会公開講座を開催して、一般市民への婦人科疾患への理解、疾病の予防、健診の重要性などの啓蒙活動を行っている。
8.医療人教育への取り組み
- i) 卒後研修教育
卒後臨床教育の取り組み 平成24年度は初期研修1・2年目研修医の産婦人科における1~3ヶ月間の研修に対しては産婦人科専門医の資格を取得した医師を指導医として1対1の対応を基本として、様々な産婦人科疾患に対する理解を深めるため偏りのない症例を経験させた。 - ii)専門医取得のための支援
産婦人科専門医は卒後5年の臨床経験を経て受験資格を有する産婦人科医必須の専門医資格であり、当院はその指導施設に指定されている。 - iii)認定施設の実績
日本産科婦人科学会専門医制度研修指導指定施設の他に日本婦人科腫瘍学会専門医制度指定修練施設、日本周産期・新生児医学会周産期母体・胎児専門医基幹研修施設、日本生殖医学会生殖医療専門医制度認定研修施設の認定を受け、専門医の認定に向けて修練を行っている。
産科
1.スタッフ

診療科長(教授) 近藤 英治(こんどう えいじ)
准教授1名、講師2名、助教4名、診療助手3名、医員11名
2.診療科の特徴、診療内容
周産期(妊娠・分娩、合併症妊娠の管理)医療、および生殖医療(不妊症における体外受精・IVF?ETなど)の領域について診療を行っている。同じく女性を診療する部門である婦人科診療と密接に協力しつつ、女性に対する全人的な診療ができるように努めている。
産科27床(継続保育室[GCU]6床を含む)で、小児科と共同で運用している総合周産母子センター内に12床の新生児集中治療室(NICU)を有し、小児科・発達小児科・小児外科と連携して、24時間体制でハイリスク新生児の管理に当たっている。
2010年10月には胎児母体集中治療室(MFICU)6床が開設され、より高いリスクの妊婦さんや新生児に対応可能となった。不妊治療については、3名の生殖医療指導医が婦人科診療スタッフ、不妊分野認定看護師や認定IVFコーディネーターと共に診療に当たり、自然妊娠の可能性を最大限に向上させるよう系統的かつ個別化した診療を行うとともに、体外受精・胚移植をはじめとした生殖補助技術(ART)を施行し、多くの妊娠例が得られている。
上記の取り組みの結果、分娩数および母体搬送数は年々増加傾向にある。また産婦人科、NICU、精神科を有する県下で唯一の医療機関として、精神疾患合併妊娠を積極的に取り扱っている。
3.診療体制
外来診療体制
外来診療は日本産科婦人科学会認定産婦人科専門医による診療を基本とし、希望者には女性医師外来を設け、さらに臨床遺伝専門医による生殖医療カウンセリングを開設している(要予約)。新来・再来の診察日は月・水・金が基本である。
病棟診療体制
月曜日午後に病棟回診、木曜日に小児科とのカンファレンスを行い、横断的な診療に努めている。すべての分娩に複数の産婦人科医が立ち会い、不測の事態に備えており、過去20年以上医療訴訟の対象となったことはない。
病棟運営では、特に平均在院日数について良好な結果を残している。
4.診療実績
1)入院患者数・分娩数
| 年 | H24 | H23 | H22 | H21 | H20 |
|---|---|---|---|---|---|
| 入院患者数 | 707 | 716 | 732 | 623 | 672 |
| 分娩数 | 315 | 312 | 306 | 275 | 261 |
2)主たる入院目的
| 年 | H24 | H23 | H22 | H21 | H20 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陣痛発来・分娩目的 | 245 | 228 | 193 | 180 | 189 |
| 流産管理 | 40 | 30 | 44 | 38 | 48 |
| 早産管理 | 92 | 95 | 130 | 74 | 94 |
| 妊娠高血圧症候群管理目的 | 28 | 36 | 26 | 29 | 23 |
| 異所性妊娠(疑い含む) | 11 | 17 | 13 | 24 | 24 |
| IVF-ET目的 | 3 | 40 | 33 | 37 | 66 |
| 異常新生児 | 184 | 198 | 207 | 153 | 132 |
| その他 | 104 | 72 | 86 | 88 | 96 |
| 計 | 707 | 716 | 732 | 623 | 672 |
3)分娩様式
経腟分娩:175例 帝王切開:140例(帝王切開率:44.4%)
4)経腟分娩時大量出血者(≧1000g)
10例(輸血例:なし)
5)多胎妊娠分娩
12例
6)早産
80例
*分娩数に占める早産の割合(%)
| 年 | H24 | H23 | H22 | H21 | H20 |
|---|---|---|---|---|---|
| /分娩数 | 25.6 | 27.2 | 27.8 | 28.7 | 25.7 |
| 22-23週 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 |
| 24-27週 | 2.9 | 5.2 | 2.3 | 3.3 | 1.9 |
| 28-32週 | 6.1 | 6.8 | 9.8 | 5.1 | 8.4 |
| 33-36週 | 16 | 15.2 | 15 | 20.4 | 14.9 |
7)過期産
3例
8)骨盤位分娩(単胎妊娠例のみ)
30例
9)帝王切開後の経腟分娩
6例
10)その他
人工妊娠中絶:10例 不妊手術:3例 妊産婦死亡:0例 他院への搬送:17例 当科への救急搬送:143例
11) 体外受精・胚移植による治療成績(H24)
| 適応 | n | cancel | retrievalfailure | 採卵 | ET | 妊娠(%/ET) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 卵管 | 12 | 0 | 0 | 12 | 8 | 1(12.5) |
| 男性 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0(0) |
| 難治性 | 52 | 5 | 7 | 40 | 16 | 0(0) |
| 子宮内膜症 | 21 | 2 | 1 | 18 | 8 | 2(25.0) |
| 計 | 92 | 7 | 8 | 77 | 67※ | 10(14.9) |
※:凍結融解胚移植32周期を含む
12) 外来診療の実績
超音波専門医の資格を有する医師により、経腹超音波断層法による胎児精査が行われており、胎児奇形が疑われる症例の紹介例が多い。
必要な症例については羊水穿刺により胎児染色体分析が行われる。出生前診断をはじめとした方針決定にあたっては複数の診療科に属する臨床遺伝専門医によって遺伝カウンセリングが行われ、夫婦の自己決定を助ける。
5.高度先進的な医療の取り組み
Turner症候群をはじめとする思春期遅発症、低身長を呈する女児に対し、身長ののびを阻害することなく二次性徴の獲得および骨塩量増加を得るためにIRBの承認を得て低用量エストロゲンの投与を行い、小児科、発達小児科、代謝内分泌内科と協力して至適な投与プログラムの作成に向けた検討を行っている。
子宮下部への異所性妊娠である子宮頸管妊娠、帝王切開創部妊娠に対するメソトレキセート局所投与による子宮温存治療を行っている。
6.臨床試験・治験の取り組み
科研費による研究
令和2年度の科研費は下記9件であった。
- ①片渕 秀隆 基盤研究(C)
環境物質の経卵管的な卵巣暴露による発癌機構の解明から導かれる卵巣癌予防の外科戦略 - ②大場 隆 基盤研究(C)
糖尿病の影響を受けた胎児の形態異常に関わる遺伝子のエピゲノム変異に関する研究 - ③田代 浩徳 基盤研究(C)
子宮頸癌前癌病変におけるYAP1活性化と内分泌環境因子との関連について - ④本原 剛志 基盤研究(C)
腫瘍随伴マクロファージの免疫学的動態の制御による卵巣癌に対する新規治療戦略の開発 - ⑤齋藤 文誉 基盤研究(C)
内分泌学的因子を包含した新たな子宮内膜癌の分類と新規治療戦略の確立 - ⑥山口 宗影 若手研究(B)
プロラクチンを介した子宮内膜癌の発癌;増殖機構の解明と新たな予防・治療戦略 - ⑦伊藤 史子 基盤研究(C)
原発性卵巣不全患者における減数分裂関連因子異常の探索 - ⑧坪木 純子 若手研究(B)
上皮性卵巣癌の治療過程におけるM2マクロファージの変化と新規治療戦略への応用 - ⑨竹下 優子 若手研究(B)
卵巣癌におけるANGPTL2標的とした新たな治療戦略の開発
7.地域医療への貢献
平成19年度に熊本県から委託を受けて天草地区における早産予防モデル事業を行い、平成21年度にその転帰をまとめて報告した。また人吉球磨地域の転帰を平成23年度に報告した。
平成24年度より熊本県全域において同様の早産モデル事業を発展・展開させている。
大場准教授は以下の委員を務めた。
- 熊本県周産期医療協議会
- 熊本県周産期搬送体制検討会
- 熊本県新生児聴覚検査推進委員会
- 熊本周産期懇話会(会長)
- また、2名の医師が委嘱され熊本県不妊相談事業における相談員を務めた。
セミナーや講演会の開催
毎年3月に日本産科婦人科学会公開講座を開催して、一般市民への産婦人科疾患への理解、疾病の予防、健診の重要性などの啓発を行っている。
8.医療人教育への取り組み
- i) 卒後臨床教育の取り組み
平成24年度は初期臨床研修医の産婦人科研修に対して、全スタッフが一致協力して教育に臨んだ。産婦人科専門医の資格を取得した医師を指導医とし1対1の対応を基本として、様々な産婦人科疾患に対する理解を深めるため偏りのない症例を経験させるべく努力した。 - ii)専門医取得のための支援
産婦人科専門医は卒後5年の臨床経験を経て受験資格を有する産婦人科医必須の専門医資格であり、当院はその指導施設に指定されている。 - iii)認定施設の実績
日本産科婦人科学会専門医制度研修指導指定施設、日本周産期・新生児医学会周産期母胎・胎児専門医の基幹研修施設、日本生殖医学会生殖医療専門医制度認定研修施設に認定されている。
9.研究活動
早産の原因として潜在的な感染症が重要視されており、絨毛膜羊膜炎のほか歯周病変が感染源として注目されている。我々は天草地区をモデル地区として絨毛膜羊膜炎と歯周病双方への介入が早産の予防に繋がるとの仮説の下に前向き検討を行い、極低出生体重児の出生数を約30%に抑制したことについて報告した(熊本県早産予防対策モデル事業:Amakusa RAINBOW Project)。さらに人吉球磨地区においても同様の成果が得られ、平成24年度からは熊本県全体で同事業を展開している。
平成22年度より環境省が行う「こどもの健康と環境に関する全国調査(エコチル調査)」のパイロット調査を、公衆衛生・医療科学、小児科学教室とともに担当し、エコチル調査の円滑な実現に向けて情報収集を行った。